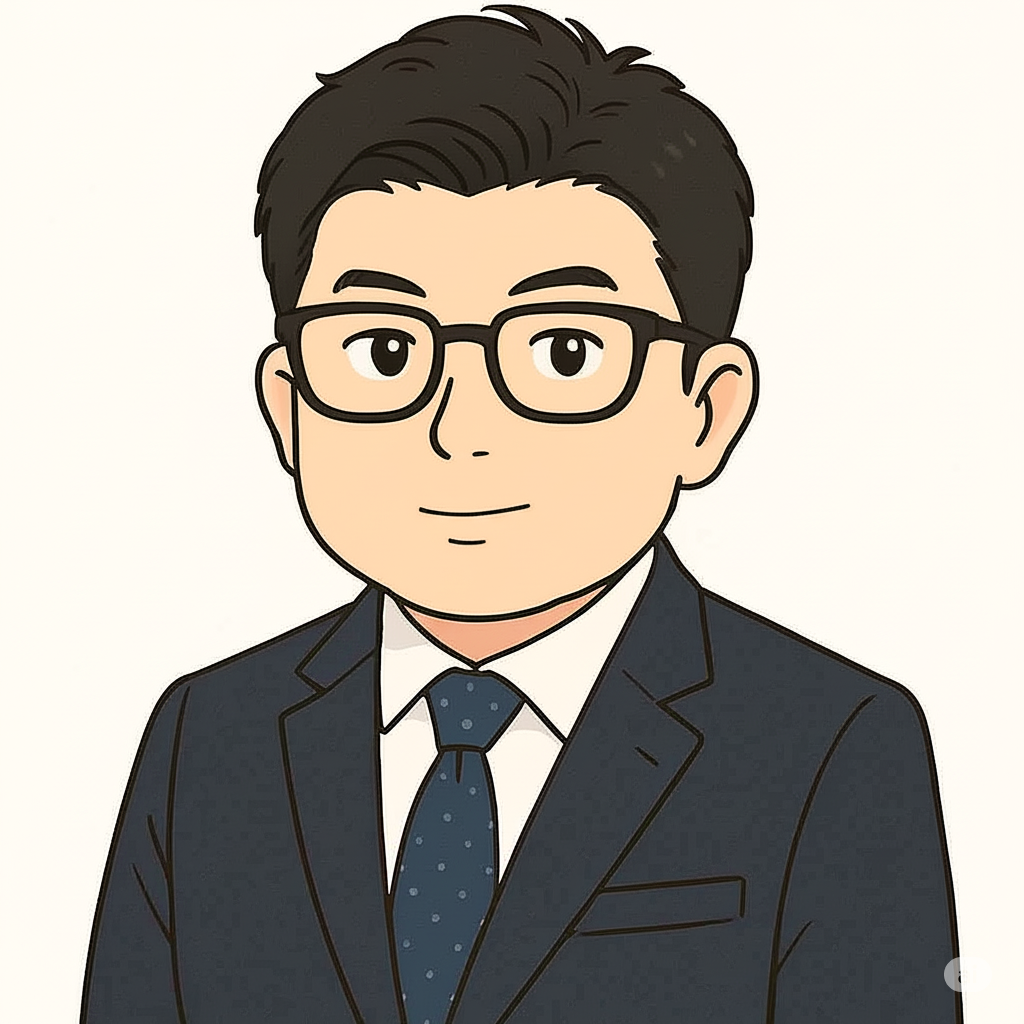前回のブログでは遺言書について解説しました。

今回は同じ相続関係の書類である遺産分割協議書について解説していきます。
遺言書にくらべて何だか難しそうな名前ですよね。
あまり聞いたことがないという方もいらっしゃると思います。
遺産分割協議書とは何か、どんな時に必要となるのかについて解説していきます。
遺産分割協議書とは何か
遺産と相続財産の違い
ところで、「遺産」と「相続財産」という言葉があります。
どちらも被相続人の財産ということは想像がつくと思いますが、その違いはどこにあるのでしょうか?
一般的には「遺産」は被相続人が所有していた現預金や不動産といった財産だけでなく、
借金や未払いの税金などの負債、年金受給権のような被相続人の一身専属権(相続の対象とならない)
といった被相続人の全ての財産を指します。
それに対し「相続財産」は「遺産」のうち相続人が相続する財産だけを指します。
前述した被相続人の一身専属権などは相続の対象とならないため相続財産には含まれていません。
負債でも、例えば被相続人が有名なデザイナーだったような場合に、何かのデザインをする契約をしていても
相続人が同じものを作成することは困難ですから、そのような契約の履行義務も相続財産には含まれません。
ただし、遺産分割というときの「遺産」は「相続財産」のこと(正しくはその一部)です。
ここは混乱しやすいのですが、この後の文章で読んでいただくことで理解が深まると思います。
遺産分割とは
相続財産について、民法という法律では各相続人が相続する割合を定めています。(法定相続)
また、被相続人が遺言書によって法定相続とは違う方法を指定できることも前回のブログで説明した通りです。
では、「遺産分割」とはどういうことなのでしょうか。
例えば亡くなられた方(以後、被相続人)には配偶者と子供1人がいた場合、法定相続の割合は
それぞれ2分の1ずつとなります。
これが現金や預金などのように分けることが容易なもの(可分債権といいます)であればよいのですが、
家や土地などの不動産や株式などの有価証券は2分の1にするといっても切り分けるわけにもいかず、
原則分けることが難しい(不可分債権といいます)ですよね。
不可分債権は法定相続の割合で「共有」することになるのですが、例えば家を売ったり誰かに貸したいと
思っても、他の共有者の合意がないと実現できず困ってしまうことになる場合もあります。
例えば遺言書で被相続人が「子供に家と土地を相続させる」としていたと仮定しましょう。
子供はすでに結婚して別の家に住んでいた場合、被相続人の家と土地は不要と考えることもあるでしょう。
その場合、売れればまだ良いですが、売れなければその家と土地を管理する手間も費用もかかってしまいます。
逆に配偶者はそれまで住んでいた家に住めない(厳密には配偶者居住権という権利がありますがここでは割愛します)
という状況に陥ってしまい大変困ることとなります。
そこで、このように法定相続や遺言書通りに相続することが相続人にとって望ましくない場合に、
相続人で話し合いをして誰が何をどれだけ相続するのかを決めることを「遺産分割協議」と呼びます。
遺産分割協議書はその話し合いの結論を文書にしたためたものとなります。
遺言書による被相続人の意思を尊重することは大事ですが、残されたものの意思を
最優先しなければならないのは当然ですよね。
遺産分割協議書は必要なのか
前述したように、法定相続や遺言書の通りに相続財産が決められると困ってしまう場合には
相続人の話し合いにより遺産分割協議書を作成して相続財産の配分を決めることができるとお伝えしました。
では、遺産分割協議書は必ず必要なものなのでしょうか。
遺産分割協議(書)が必要ない場合とは
①相続人が1人だけだった場合
相続人が配偶者だけ、子供だけなど1人しかいない場合は、全ての相続財産がその1人のものになりますので、
当然ながら遺産分割協議は必要ありません。
②遺言書の内容どおりの相続をする場合
遺言書の内容を相続人全員が納得してそれに従うのであれば、遺産分割協議をする必要はありません。
ただし、実際には不動産の名義変更手続きなどは遺産分割協議書がないと受付されない場合もあります。
また、遺言書に記載されていない財産があったときは分割協議が必要となるでしょう。
遺産分割協議書を作成しなかったらどうなるのか
では、遺産分割協議書を作成しなかったらどういった影響があるのでしょうか。
①相続の手続きができない・進まない
例えば子供1人が家を相続した場合、遺産分割協議書がないとその事実を証明できません。
そうなると家の名義変更手続きもできませんし、家を処分することも難しくなります。
②相続人同士のトラブルに発展する
せっかく協議をして分割方法が決まったとしても、それをしっかり文書にしておかなければ、
後で言った・言わないの水掛け論となってしまうこともあります。
トラブルとなり訴訟に発展してしまうようなケースも想定されます。
③共有状態による管理の煩雑化
遺産分割協議書を作成しないと、不可分債権は相続人の共有財産となります。
前述したように、共有財産は共有者1人だけでできることには限界があります。
他の共有者の同意がなければ出来ないことも多く、管理費なども持分に応じて負担する必要があります。
④税制上の優遇措置を受けることができない
相続税の申告・納付には遺産分割協議書が必要となる場合があります。配偶者の税額軽減や小規模住宅地等の
特例などの適用を受けるには遺産分割協議書の提出が必要となることがあります。
まとめ
ここまで遺産分割協議書について解説してきましたが、最後にまとめます。
遺産分割協議は被相続人の相続財産について、相続人同士がその配分の割合や方法を
話し合いで決めることであり、遺産分割協議書はその決定事項を文書としたものとなります。
遺産分割協議書がないと、相続の手続きに支障をきたすこととなりますし、相続人同士で
トラブルに発展してしまうこともありますので、相続人が1人だけの場合を除き作成するのが
望ましいでしょう。
ただ、遺産分割協議書の作成には法的な知識が必要となりますし、被相続人の財産調査や
相続人が誰なのかを確定(実は隠し子がいたなんてことも・・・)する必要あります。
そういった点からも手続きは専門家に相談して進めていくほうがよいでしょう。
もっと詳細を確認したい、相続人同士のトラブルを避け円満に手続きを進めたいという方は
ぜひ専門である行政書士にご相談ください。
遺産分割協議書の作成をお考えであれば、まずはご相談だけでも構いません。
お気軽に当事務所までご連絡ください。
⇩
行政書士こやなぎ事務所のホームページはこちら