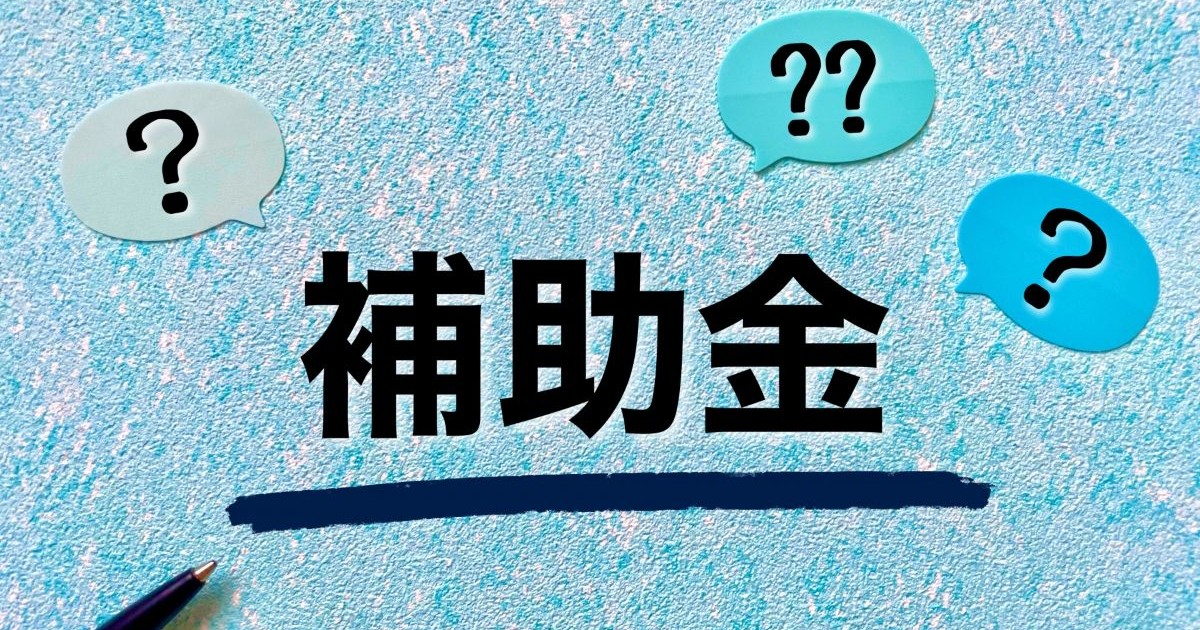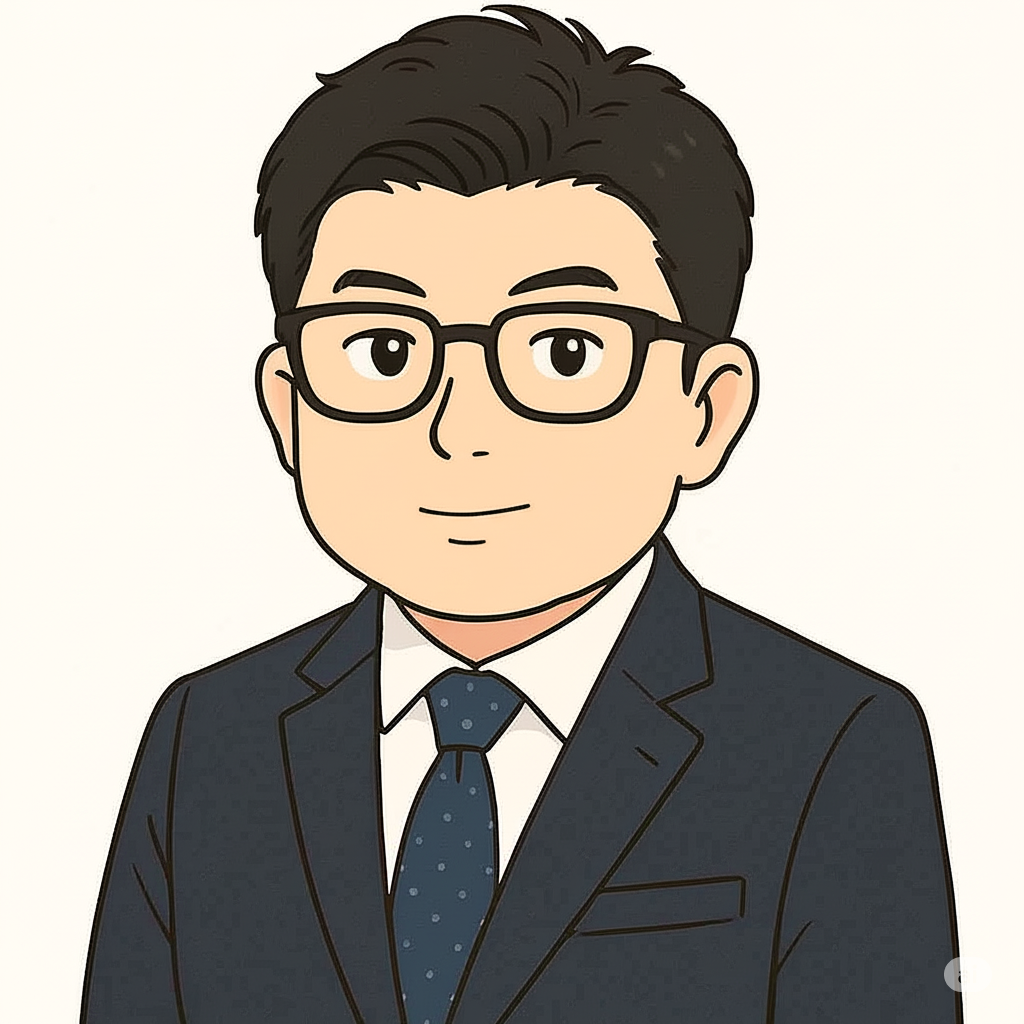みなさんも新聞やニュースなどで補助金や助成金、給付金といった「何かお金がもらえそう」なキーワードをご覧になったことがあると思います。
しかし、それらの違いやどういったときにお金がもらえるのかを正しく理解している方はそう多くないのではないでしょうか。
今回はそれらの違いや特徴、活用方法などについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
補助金・助成金・給付金の違いとは
行政書士として、ご相談者様から「補助金と助成金って何が違うの?」と聞かれることは少なくありません。また、コロナ禍で広く知られるようになった「給付金」も加わり、それぞれの違いがさらに分かりにくくなっています。これらを混同すると、事業計画や資金調達の選択肢を誤るリスクがあります。まずは、それぞれの本質的な違いを明確に理解しましょう。
| 種類 | 所管官庁 | 主な目的 | 公募方式 | 採択率 | 予算 |
| 補助金 | 経済産業省、地方自治体 | 新規事業、設備投資など政策目的の推進 | 公募制、審査あり | 競争的、採択率が低い | 年度ごとに予算が設定され、予算上限に達すると終了 |
| 助成金 | 厚生労働省 | 雇用促進、人材育成、労働環境改善など | 通年、要件を満たせば原則受給可能 | 比較的高い(要件を満たせばほぼ100%) | 通年で予算が設定されることが多い |
| 給付金 | 内閣府、地方自治体 | 緊急事態や一時的な困窮への支援 | 申請要件を満たせば受給可能 | ほぼ100% | 国会で追加予算が承認されることも多い |
補助金:事業者が行う「事業」を支援する
補助金は、主に経済産業省が所管し、国の政策目的を達成するために、事業者の新たな挑戦や新型設備の導入を支援することを目的としています。例として、中小企業の生産性向上、新規事業の立ち上げ、IT導入などが挙げられます。最も大きな特徴は、公募制であり、採択審査がある点です。申請書類(事業計画書)の質や、その事業が政策目標にどれだけ合致しているかが厳しく審査されるため、競争率は非常に高いのが実情です。そのため、採択されるためには、緻密な事業計画と説得力のある書類作成が不可欠となります。また、補助金は基本的に後払いです。事業実施後、かかった経費を精算し、その一部が支給されます。
助成金:要件達成による支援
助成金は、主に厚生労働省が所管し、雇用維持、人材育成、労働環境改善など、労働分野における課題解決を目的としています。補助金と異なり、多くの場合、通年で公募されています。そして、もっとも重要な違いは、申請要件をすべて満たせば、原則として受給できるという点です。競争倍率という概念はほとんどなく、要件さえ満たせばほぼ100%の採択率を誇ります。手続きも比較的シンプルで、必要な書類を揃えて提出すれば良いことが多いため、計画的な活用がしやすいメリットがあります。尚、東京都の助成金は名称こそ助成金となっておりますが、内容としてはほとんどが補助金に該当するものとなっております。
給付金:緊急事態への迅速な対応
給付金は、災害、パンデミック、経済危機など、特定の事象によって発生した困難な状況にある個人や事業者を緊急的に支援することを目的としています。多くの場合、内閣府や地方自治体が主体となり、迅速な支給が求められます。受給要件はシンプルで、例えば「売上が前年比〇%以上減少した」といった明確な基準が設けられています。申請期間が短く設定されることもあり、迅速な情報収集と申請手続きが重要となります。
主な補助金の種類と活用法
代表的な補助金を3つご紹介します。いずれも、事業者の成長戦略に貢献できるものとなっております。
1. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)
製造業、サービス業など幅広い業種の中小企業が対象となる、経済産業省の看板補助金です。革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善など、生産性向上に資する設備投資やシステム構築を支援します。採択の鍵は、事業計画の革新性と、生産性向上の明確な目標設定です。例えば、「最新鋭の工作機械を導入して、製造リードタイムを〇%短縮する」「AIを活用した顧客管理システムを構築し、受注率を〇%向上させる」といった具体的な計画が求められます。
2. 小規模事業者持続化補助金
従業員数が少ない小規模事業者が対象の補助金です。販路開拓や業務効率化を目的とした取り組みを支援します。具体的には、ウェブサイト制作、チラシ・パンフレット作成、展示会出展費用、新たな顧客管理システムの導入など、比較的少額の経費を対象としています。この補助金の魅力は、比較的採択率が高く、手続きもシンプルであることです。事業計画書のフォーマットが定められているため、それに沿って丁寧に作成すれば、十分に採択のチャンスがあります。
3. 事業再構築補助金
コロナ禍で生まれた大型補助金で、中堅・中小企業がポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、事業の再構築を支援することが目的です。既存事業を縮小・廃止し、新たな事業へ転換する、新分野へ進出する、などの大胆な挑戦を後押しします。補助額が非常に大きく、億単位の支援も可能です。しかし、その分、事業計画の審査も厳格で、市場分析、競争優位性、収益性の根拠を詳細に記述した事業計画書が求められます。
誰がどのように活用できるか?
これらの補助金・助成金は、単なる資金調達の手段ではありません。むしろ、事業者が抱える課題を解決し、次のステージへ進むための戦略ツールと捉えるべきです。
誰が、どのように活用すべきなのか、ここでは一例をあげてみました。
- 新たな設備投資を検討している中小企業様
ものづくり補助金を活用し、最新鋭の機械導入による生産性向上を図る。 - ウェブサイトをリニューアルしたい、集客に悩む個人事業主様
小規模事業者持続化補助金を活用した販促計画を立案。 - コロナ禍で売上が減少し、新たな事業への転換を考えている飲食店様や小売店様
事業再構築補助金を活用し、デリバリー事業やECサイト構築など、新分野への挑戦をサポート。 - 人材の定着や育成に課題を持つ企業様
人材開発支援助成金など、厚生労働省系の助成金を活用し、社員研修の導入や資格取得費用の負担を軽減。
補助金活用の注意点
このように、補助金を活用することにより事業の拡大・成長が見込める非常に有効な手段となりえますが、いくつかの注意点があります。
- 事業完了後の後払いであること
補助金が支払われるのは事前に申請した事業計画の事業が完了した後となります。つまり補助金にかかわる事業の支払いは自己資金や借入金等により支払う必要があります。事業計画に沿った資金繰りを考慮する必要があります。 - 補助される金額は事業計画の全額ではないこと
補助金は事業計画に必要な資金の2分の1、3分の2など支払額(補助率)が定められており、全額を支払うような補助金はほぼありません。補助金が支給されない分は自己負担となります。 - 一部、返還が必要な場合もあること
補助金は原則として返還義務がありませんが、一部の補助金では補助事業により一定の収益があった場合には、補助金を一部返還しなければならないものもあります。もちろん、不正受給や補助金の目的外使用が判明した場合、導入した設備を補助事業者への申請をせず処分(売却等含む)した場合も返還を求められるケースがあります。 - 事業の経過報告や完了報告が必要であること
補助事業の進捗状況や完了後の一定期間に補助事業者への経過報告が必要です。特に経費の支払いについては仕様書、見積書、注文書、請求書といった経理書類と呼ばれる証票類が必要となります。こういった書類について適切に管理することが求められます。 - 補助金は収入となること
補助金は収入となるため法人税や所得税に影響します。あらかじめ顧問税理士に相談するなどして事業への影響を考慮して活用する必要があります。
まとめ
補助金、助成金、給付金は、それぞれ異なる目的と性質を持っています。これらを正しく理解し、自社の事業計画や経営課題に合わせて活用することが、持続的な成長への鍵となります。
しかし特に、補助金は採択率が低く、申請書類の作成には専門的な知識が不可欠です。また、無事に採択され補助金を受給した後も事業報告や経費精算といった事務手続きも煩雑です。
行政書士は、単に書類作成を代行するだけでなく、事業者の「想い」や「ビジョン」を汲み取り、それを論理的かつ説得力のある事業計画書へと落とし込むことができます。事業再構築補助金のような大型案件では、専門家の支援がなければ採択は難しいでしょう。また、補助金受給後の事業報告や経費精算の手続きも煩雑であり、行政書士はこうしたアフターフォローまで一貫してサポートすることが可能です。
また、補助金が支給されるまでの間は自己資金や借入金により経費の支払いが必要となりますが、銀行等の金融機関にその間の資金繰りについて相談が必要なこともあります。その場合も金融機関に同行し、事業計画の内容説明により融資等につなげることも支援いたします。
※厚生労働省が所管する「助成金」については、そのほとんどが社会保険労務士の独占業務であり、行政書士は関与することができません。
補助金のご活用をお考えであれば、まずはご相談だけでも構いません。
お気軽に当事務所までご連絡ください。
厚生労働省が所管する助成金についても、信頼できる社会保険労務士をご紹介いたします。
⇩
行政書士こやなぎ事務所のホームページはこちら