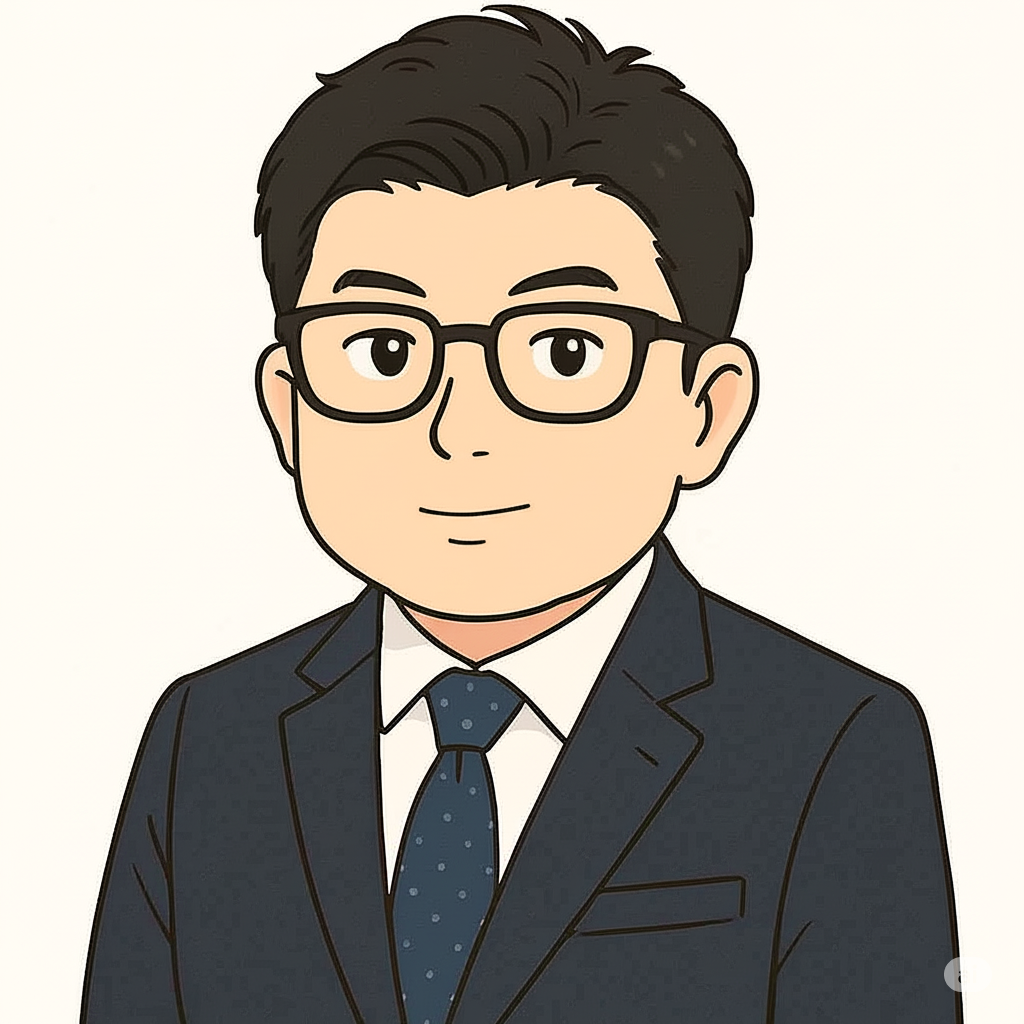はじめに:なぜ農地の売買・貸借には「許可」が必要なのか?
日本の農業は、深刻な課題に直面しています。特に、農業に従事する方の減少と高齢化は、農地の担い手不足を加速させ、耕作放棄地の増加や農業生産力の維持に大きな影響を与えています。(基幹的農業従事者は65歳以上の方の割合が70%以上となっています)
一方で、都会から田舎への移住等により、新しく農業を始めたいという方も一定数いらっしゃいます。
このような状況で、大切な食料生産の基盤である農地を守り、効率的かつ安定的な農業経営に活用されるように定められているのが農地法です。農地法は、単に土地の取引を規制するだけでなく、日本の農業の未来を守るための重要な法律なのです。
その中でも、農地を耕作目的で売買したり、貸し借りしたりする際に適用されるのが農地法第3条です。
農地法第3条の概要:「農地」を「農地のまま」使用する
農地法第3条は、「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」に、原則として農業委員会等の許可が必要であると定めています(農地法第3条第1項)。
簡単に言えば、「農地を、引き続き農地として使う目的で」 権利を移転する(売買、贈与など)または設定する(貸借など)場合に、この許可が必要です。
この規定の目的は、
- 農地の買占めや投機の防止: 農業者ではない人が、資産目的や投機目的で農地を取得することを防ぎます。
- 農地の効率的な利用: 地域の農業生産力を維持・向上させるため、農地を適切に耕作できる担い手に集約・利用させることです。
許可を受けずに行った売買契約などは、法律上その効力を生じません。これは、農地の確保という公共の利益を守るための、非常に強い規制です。
第3条許可の主な要件:誰でも農地を買えるわけではない
農業委員会が許可を出すかどうかを審査する際の主な基準は、権利を取得しようとする者が、その農地を適切に、かつ効率的に耕作できるかどうかという点にあります。具体的な要件(許可基準)の一部をご紹介します。
1. 全部効率利用要件(効率的な経営の確保)
申請者が、今回取得する農地を含め、所有または借りているすべての農地を、適切に管理し、効率的に利用すると認められること(農機具、労働力、技術などがあるか)。
2. 農作業常時従事要件(担い手の確保)
権利を取得しようとする者またはその世帯員が、その農地で農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められること。原則として、年間150日以上の従事が一つの目安とされています。これは、農業に従事する方の減少が進む状況において、本気で農業に取り組む担い手に農地を委ねるための重要な要件です。
3. 地域との調和要件
権利の取得が、周辺の農地の集団的な利用や、農作業の効率的な実施に支障を及ぼさないと認められること。
4. 法人の要件(農地所有適格法人など)
法人が農地を取得する場合、原則として「農地所有適格法人」である必要があります。これは、農業を事業の中心とし、構成員や事業形態などについて法律で定められた要件を満たす法人です。
関連する法令との関わり:農業経営基盤強化促進法など
農地の権利移動には、農地法だけでなく、関連する法律も深く関わってきます。
- 農業経営基盤強化促進法: 農業委員会を介さず、市町村が策定する「利用権設定等促進事業」を通じて、農地中間管理機構(農地バンク)などを活用し、より円滑に農地の貸し借りが行える仕組みがあります。この手続きによる貸借などは、農地法第3条の許可が不要となる特例があります。
- 都市計画法・建築基準法: 第3条許可は「農地として利用し続けること」が前提のため、都市計画法や建築基準法が定める建物の建築などに関する規制は直接適用されません。しかし、将来的に農地を宅地などに変える(転用)際にはこれらの法律が関わってきます。
まとめ
今回は農地法第3条について解説しました。次回は農地法第4条で、自己所有の農地を農地以外の目的(宅地等)で使用するために必要となる手続きについて解説します。
農地法第3条の許可申請は、必要な書類が多く、許可要件の判断には専門的な知識が必要です。また、農業委員会との事前協議等もあり、現地にて立ち合いをすることもあります。
行政書士は、お客様の営農計画をヒアリングし、要件を満たしているかを事前に確認し、許可申請書の作成から農業委員会との調整までをサポートすることで、農地の権利移動をスムーズに実現するためのお手伝いをします。
農業への参入を検討されている方、農地を別の就農者への売却・賃貸をご検討の方は、まずはご相談だけでも構いません。
お気軽に当事務所までご連絡ください。
⇩
行政書士こやなぎ事務所のホームページはこちら