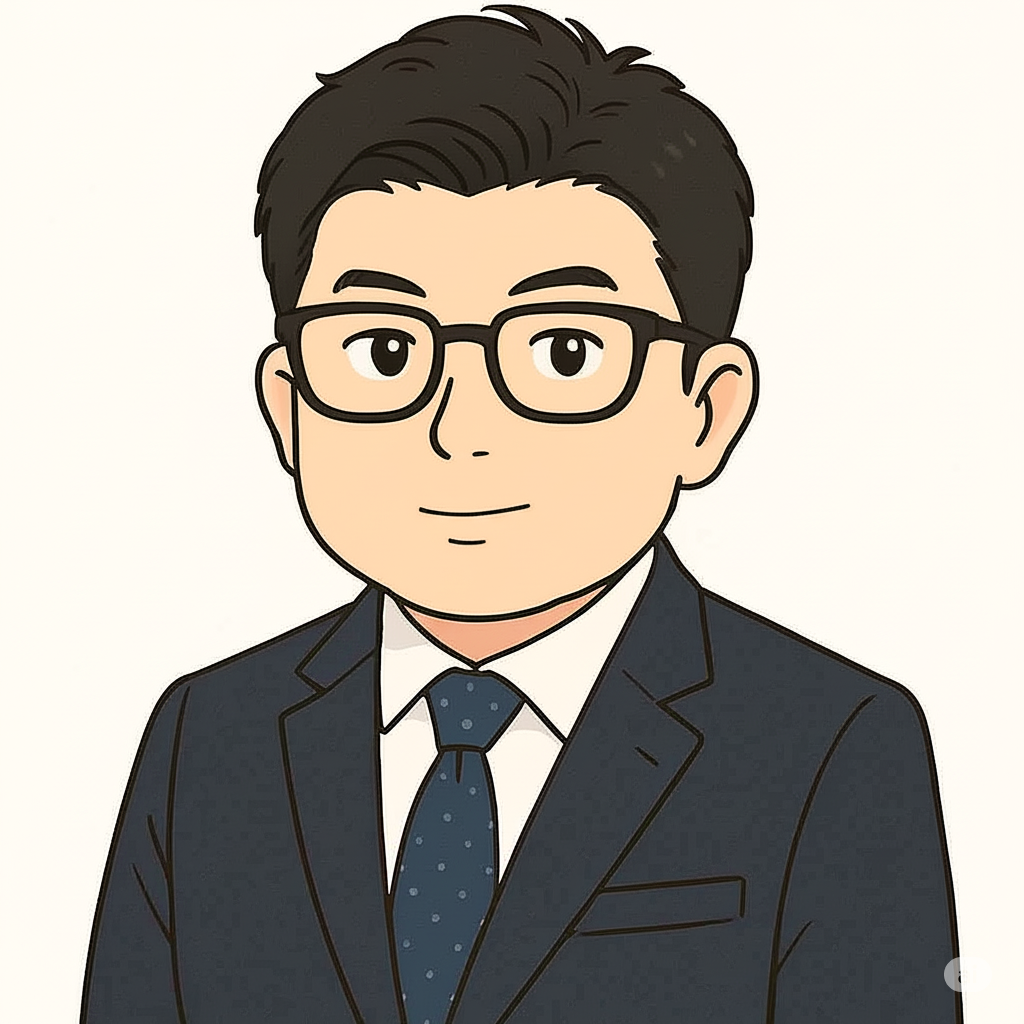前回は農地法第4条について解説しました。

今回は農地法第5条について解説していきます。
農地法第5条とは?:転用と権利移動を同時に行う
農地法第4条が、所有者自身が農地を転用する場合(自己転用)のルールであるのに対し、農地法第5条は、農地の所有権の移転や貸借などの権利設定を伴い、かつ、その農地を農地以外の用途に転用する場合のルールを定めています。
例えば、「農地を買い受けて、そこに住宅を建てる」というケースが、まさに第5条の典型的な適用場面です。
この第5条は、「農地の権利移動(第3条の要素)」と「農地転用(第4条の要素)」の二つの行為を同時に行うため、農地法の中でも非常に重要な規定となっています。
農地法第5条の概要:知事等の許可が必要な複合行為
農地法第5条第1項は、「農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするため、これらの権利を設定し、又は移転する場合」には、原則として都道府県知事等の許可が必要であると定めています。
この規定により、例えば、買主が農地を購入し、その農地を宅地として利用する目的で所有権を移転する場合、売主と買主が共同して知事等へ許可申請を行う必要があります。
許可を受けずに行った契約は、その効力を生じません。第5条は、優良農地の保全と、農地が健全な利用目的に供されることを確保することを目的としています。
許可の基準:第4条と同様の立地・一般基準
第5条の許可基準は、基本的に第4条と同様の「立地基準」と「一般基準」が適用されます。
1.立地基準:農地のランクによる区分
優良(上位ランクの)農地からの転用を抑制するため、農地のランク(農用地区域内農地、甲種・第1種・第2種・第3種農地)に応じた規制が設けられています。
原則不許可となる農用地区域内農地や甲種・第1種農地からの転用は、特に厳しく審査され、公共性の高い事業など限定的な例外を除き、許可を得るのは困難です。
2. 一般基準:事業計画の確実性
転用後の事業計画の実現性や、周辺農地への影響を防ぐための措置が審査されます。
- 転用事業の確実性: 転用後の建設計画や利用計画が、必要な資金や資力、他の法令による許認可の見込みから見て、確実に実施されること。
- 周辺農地への被害防止: 転用によって、周辺の農地の水利や日照、土壌などに悪影響を与えないよう、適切な対策が講じられること。
関連する法令との関わり:都市計画法・建築基準法の同時適用
第5条の許可申請は、農地法だけでなく、都市計画法や建築基準法などの他法令との調整が特に重要になります。転用後の土地利用を実現するためには、農地法の許可と並行して、これらの法令による手続きも必要になるからです。
- 都市計画法による開発許可: 一定規模以上の開発行為(宅地造成など)を伴う転用の場合、農地法の許可とは別に、都市計画法に基づく開発許可が必要になります。特に、市街化調整区域では、開発行為自体が厳しく規制されており、開発許可を得るための要件が非常に複雑です。
- 建築基準法による建築確認: 転用後の土地に建物を建てる際には、建築確認を受け、建築基準法の基準(建物の構造、用途、高さなど)をクリアしなければなりません。
これらの法令の許可・確認が得られなければ、農地法の許可は取り消しになることもあります。第5条の申請は、「農地法」と「都市計画法」の許可をセットで検討することが不可欠です。
- 市街化区域内の特例: 第4条と同様に、市街化区域内の農地を転用目的で権利移動する場合、知事等の許可は不要となり、事前に農業委員会への届出で済みます。
まとめ
農地法第5条の申請は、売買や貸借という当事者間の合意に加え、農地転用という行政規制が絡む、非常に複雑な手続きです。確実に手続きを進めるためにも、専門家に相談されることをお勧めします。
行政書士は
- 農地法上の許可要件(立地・一般基準)のクリア
- 都市計画法、建築基準法などの他法令との調整
- 売主様・買主様(貸主様・借主様)双方の意向の調整
- 必要書類の収集・作成
- 農業委員会や土地改良区等の関係機関との調整
といった、多岐にわたる課題を一元的に解決し、農地の転用をサポートいたします。
農地を宅地や駐車場としての利用をご検討の方は、まずはご相談だけでも構いません。
お気軽に当事務所までご連絡ください。
⇩
行政書士こやなぎ事務所のホームページはこちら